みなさんこんばんは(^.^)
温かかったり寒かったりと忙しい気候ですが、いかがお過ごしでしょうか。
さて、今日も『パイドン』(プラトン著 岩田靖夫訳 岩波文庫)よりソクラテスの考え方をご紹介したいと思います。
ソクラテスは自然学の研究に対して期待を抱いていたという話が出てきます。
『それは例えば大地が平たいかまるいかを告げてくれるだろう、そしてそのことの原因と必然性を詳しく説明してくれるだろう。
さらにまた、太陽についても月についてもその他の星々についても、それらの運行についてやその他の諸現象についてこれらの作用をなしたり他からこうむったりすることが、いったいどういう意味でより善いのかを学べるものとね』(同書P125)
ソクラテスは何が最高最善であるかを考えること以外に、私たちにとってふさわしいことは何一つないと本書の中で言っていますが、自然学の研究は各々のものごとの原因と万物に共通の原因とを探究していくことで、それらに共通の善または理性(ヌース)による秩序を見出すことができるだろうと期待していたようです。
しかしある研究者の理論ではいろいろなものごとの原因を物質的なものによる説明だけで終わってしまっているので落胆したということを言っています。
その具体的な例を以下にご紹介しましょう。(同書P126~127)
『(その人の理論で言うと)いまここに(刑務所に)僕が座っていることの原因についていえばこんなことになる。
僕の身体は骨と腱から形作られており、骨は固くて相互に分離していながら関節でつながっている。
腱は伸び縮みできて、肉や皮膚とともに骨をつつみ、皮膚がこれらすべてのものを一つのものにまとめている。
そこで、骨は関節の中で自由に揺れ動くのだから、腱が伸びたり縮んだりすることによって、僕はいま脚を折り曲げることができるのであり、この原因によって僕はここで脚を折り曲げて座っているのである、と』
『 だが、本当の原因とは次のことである。
アテナイ人たちが僕に有罪の判決をくだすことをより善いと思ったこと、それゆえに僕もまたここに座っているのをより善いと思ったこと、そして、かれらがどんな刑罰を命ずるにせよ留まってそれを受けるのがより正しいと思ったこと、このことなのである 』
(ソクラテスは国家が信じる神々と異なる神を信じ、若者たちを誤った方向に導いたとして裁判にかけられ死刑が確定していました)
ものごとの原因を見る時に、その手段や現象(ここでは骨や腱などのこと)について説明をしてもそれでは原因の探究になっていないということですね。
ソクラテスは理性によって行動しているのですから、その理性について探究したいわけですが、それが現象の説明で終わってしまうと、まるで現象が原因であるかのような話になってしまうわけですね。
万物は可能な限り最善であるように配置されていて、このことを可能にした力を求めること、またその力の神秘的な強さについて考えるということをソクラテスは望んでいましたので、当時の自然学の理論には納得できなかったということでしょう。
私はこの“原因を探究する目的”についての話を読んで、これはいろいろな分野において応用できるとらえ方ではないかと思いました。
それは占星術についても同じようなことが言えるのではないかと思います。
占星術は人間にとって善となるための道具であると私は考えています。
自分の才能や美徳、力を知り、それらをより発揮していくことができるように星たちが促してくれる道具だと思っています。
ひとり一人星回りは違います。
どのような星回りを持って生まれてきたか(出生ホロスコープ)、過去・現在・未来の星回りと出生ホロスコープとの兼ね合い、などを観ていきますが、その星回りがどういう意味で“より善いのか”を観ていくということが大切だろうと思っています。
一人一人に与えられた星回りが、その方にとって最善なんだと考えて、その星回りの意味を探究していくことができるわけですね。
そこに理性(ヌース)の秩序というものを見出していくことができるということだと思います。
しかし、せっかく星を読んでもクライアントの人生で起きた現象の指摘で終わったり、占星術的技法の追究自体が喜びや目的となってしまうと、なぜその星回りがその方にとって必要なのかということや、クライアントの人生の出来事の意味を探究するという大事なことを忘れてしまうことになりかねません。
星を読むことが、クライアントの力と自信を増強するような機会とならなければ意味がないかもしれません。

自然科学によって様々な物理的法則が明らかにされ、広大な宇宙の話からニュートリノなどのミクロの世界まで人類の理解は深まってきました。
それは本当に素晴らしいことですね。
ソクラテスが言いたかったことは、ものごとが起こる法則や仕組みを考えることは素晴らしいけれども、目に見えない領域といいますか、宇宙の秩序であったり、天の配剤ということを法則や仕組みの先に見据えて(みすえて)考えてみるということが大切だということではないかと思います。
ちょっとややこしい話になりましたが(笑)、今日も最後まで読んでくださいまして、ありがとうございます(*^_^*)
皆さまが天使やマスター、星たちの祝福と共にありますように☆
みなさんこんばんは☆
東日本大震災から丸5年が経ちましたね。
犠牲になられた方々のご冥福を心よりお祈りします。
今日は『パイドン』(プラトン著・岩田靖夫訳・岩波書店)の中からソクラテスの弟子であるシミアスの反論の部分を取り上げたいと思います。(同書P92~)
ソクラテスの“魂は肉体が存在する以前から存在しているものであり、不滅である”との考えに対して、シミアスが反論します。
それは、魂とは竪琴や弦から生み出される和音と同じような「調和的なもの」ではないかと。
ひとたび竪琴が壊れたり、弦が切れたりしたならば、和音(調和)も滅びてしまうので、人間においても肉体が滅びたら魂も一緒に滅びるのではないかという反論です。
それに対してソクラテスが答えます。
魂が調和であるならば、魂を作っている要素(人間であれば肉体な構成要素、和音であれば竪琴や弦)には決して反対することはできずに、魂はそれらの要素に随って(したがって)いくことになるだろう。
しかし魂は肉体に随うものではないことをホメロスの詩を引用して説明しています。
(同書P117~)
「彼は胸を打ち、自分の心をこう言って叱った
耐え忍べ、わが心よ、お前は昔もっと恥ずかしいことに耐えたではないか」
魂は肉体のいろいろな要素や状態に引きずり回されるものではなく、反対に引きずり回すものであり、要素や状態の主人となるものであり、調和というような在り方のものよりは、はるかに神的ななにものかである、と。
たとえば肉体の中に熱と乾きがある時に、魂は反対の方へ、つまり、飲まない方へと引っ張るのであり、飢えが内在する時には、食べない方へと引っ張るのであるとも言っています。
これは何も過酷な修行を勧めているわけでも、自殺を勧めているわけでもありませんね。
肉体の欲望に引きずり回されるのではなく、魂が肉体を支配するのであり、魂にとって正しいことのためには肉体からの要望とは反対のことをする必要もあるということでしょう。
ソクラテスの説明にシミアスも同意しました。
シミアスの理論の“魂は調和的なものである”という前提が見直されたと言えますね。
魂が肉体と共に滅びるのでないということは、先の大震災でお亡くなりになったたくさん
の方々の魂や動物たちの魂も存在し続けているということになります。
たくさんの魂が今生きている私たちを見守ってくれていると思います。
ご冥福をお祈りするとともに、今、そしてこれからの自分自身の生き方について改めて見つめてみたいと思います。
今日も最後まで読んでくださいまして、ありがとうございましたm(__)m
すべての魂が宇宙の恵みと共にあることを祈ります☆

みなさんおはようございます(^_^)
何だか急に暖かくなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。
さて、今日は『パイドン』(プラトン著・岩田靖夫訳・岩波書店)の中から人間嫌いと言論嫌いについてご紹介したいと思います。
古代ギリシャの哲学者ソクラテスが人間嫌いについて語っています。
人が人間嫌いになるのは、ある人を盲目的に信じ、信頼できる人物だと考えた後に、しばらく経ってからその人の性格が悪く信頼できないことに気付くからだと。
そして他の人との間においてもまた同じような体験をして、それを繰り返すと、とりわけ最も親しいと考えていた人との間でそのような仕打ちを受けると遂には怒りが爆発してすべての人を憎むようになり、健全な人間などいないと考えるようになるといいます。
両親や兄弟、子供、パートナー、親友や教師、職場の上司・同僚・部下、聖職者etc…..人間でつまずくということがありますね。
しかしソクラテスは言います。(同書P103~)
人間嫌いになるのは、人間的な事柄についての心得(こころえ)もなしに人々と付き合おうとしたためだと。
もしも心得をもって人々と付き合ったのなら、非常な善人も非常な悪人も共にごく少数で、大部分の人はその中間にある、ということを考えられただろうと。
私たちは善悪の両端を意識してしまいがちですが、最高の善と最低の悪だけが存在するのではなく、むしろその中間の善も悪も混在しているグラデーションのような領域こそが多くの場合当てはまるということでしょう。
そうすると、完全に正しい人も、完全に間違った人もいないと考える方が適切だということになりますね。
完全に正しいと信じていた相手にちょっと違う面が見えてくることでショックを受けるわけですから、人を完全に正しいと盲信することは危険をはらんでいると言えるでしょう。

そこでソクラテスは言論嫌いについても語ります。
言論嫌いもある面で人間嫌いに似ていると言います。
それはある言論を真実であると信じ込み、しかしその後それを偽りであると思うような時に言論嫌いは起こります。
そういう経験が繰り返されるにつれて言論嫌いは人間嫌いと似てくるわけですね。
この言論嫌いも言論についての心得を持っていなかったために起きるものだと言います。
その心得とは、私たちは言論についての充分な知識を持っていないという考え方のことなんですね。
先ずはこの考えを受け容れるようにしていくことが大切ということですね。
そして健全な言論、真理や知識であるように努力していかなければならないということです。
それは知を愛するという哲学の意味そのものでもあるでしょう。
ソクラテスは弟子たちにこう言っています。(同書P107)
「もしも僕がなにか真実を語っていると思われるならば、同意してくれたまえ。もしそう思われなければ、あらゆる議論を用いて、それに抵抗してくれたまえ」
ソクラテスほどの哲学者がこのような事を言うのもなんだか謙遜しているように思えますが、この言葉は本気で語られた言葉であろうと思います。
なぜならソクラテスが求めるのは、自分の評判や名誉ではなくて、真理が探究されることでしょうから。
弟子にも真理を探究する姿勢を持ち続けてほしいというのが、知を愛するソクラテスが最も望むことだろうと思います。
そのためにどのような信頼できる存在また権威ある存在から出た言葉であっても、鵜呑み(うのみ)にしてはいけないという警告を弟子たちにしているわけですね。
自分で本当にそれは真実かどうか考えてみること、感じてみることが大切だということでしょう。
人間嫌いにも言論嫌いにも「心得」の有無が関わっていますね。
今日も最後まで読んでくださいまして、ありがとうございました(*^_^*)
こんばんは(^.^)
今日の熊本は温かい「建国記念の日」となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて、例のごとく『パイドン』(プラトン著 岩田靖夫訳 岩波文庫)を参考にしながら古代ギリシャの叡智をお伝えしたいと思います☆
ソクラテスは本当の哲学者の魂は快楽や、欲望や、苦痛、恐怖などをできる限り抑制するのだと弟子のケベスに語ります。
そしてなぜそれらを抑制するかという理由について彼はこう語ります。
(同書P85~86)
ソクラテス「人間があまりに強烈な快楽や、恐怖や、苦痛や、欲望を味わうと、それらの激情から、ただ単に、身体を駄目にしてしまうとか、欲望のために財産を台無しにしてしまうとか、そんな程度の悪を蒙るばかりではなくて、あらゆる悪のうちで最大にして究極の悪を蒙るのであり、しかも人々はそのことを考えてもみないのである」
ケベス「その最大にして究極の悪とはなんでしょうか、ソクラテス」
ソクラテス「すべての人の魂は、なにか激しい快楽や苦痛を感じると、それと同時に、もっともそういうものに感覚を与えるものこそ、もっとも明白でもっとも真実である―――と思い込まされる、ということだ。そういう思い込みを与えるものは、とりわけ、目に見えるものである。このような状態において魂はもっとも肉体によってしばりつけられるのではないだろうか」
ケベス「どうしてですか?」
ソクラテス「その訳はこうだ。どんな快楽や苦痛でもなにか釘のようなものを持っていて、魂を肉体に釘付けにして、ピンで留めてしまい、魂を肉体の性質を帯びたものにして、その結果、魂は、肉体が肯定することならなんでも真実である、と思い込むようになる。」
ソクラテスは、目に見えるものによって、それが真実だと思い込んでしまうことが“究極の悪”だと言っているわけですね。
続けて彼はこう語ります。
もし、魂が情念から解放された平安を獲得し、理性的思考に従い、真なるもの、神的なものを見つめ、生きていくならば...そして死んだ後には、神的なもののもとに到達し、人間的なもろもろの悪から解放される、考えるならば...魂がそのように育まれていれば何も恐れることはない、と。
地上の世界の快楽や、欲望や、苦痛、恐怖にとらわれないことで、魂が平安を獲得し、神的なものと触れることができ、死ぬことの恐れもなくなるということでしょう。
この話からはお釈迦様が得られた“解脱“を思い起こします。
お釈迦様は35歳の時にブッダガヤの菩提樹(ボダイジュ)の木の下で悟りをひらかれ、解脱されたと言われています。
解脱とは俗世間の煩悩(ぼんのう)から離れ、安らかで自由な境地を得ることをいいます。
まさにソクラテスが語っていることと同じことではないでしょうか。
お釈迦様がお生まれになった年については、紀元前600年代から400年代まで諸説ありますが、もし400年代にお生まれになっていたとしたら、ギリシャのソクラテスと同じ時代に生きていたことになります。
同じ時代の西洋と東洋に偉大な哲人が存在して、共に魂の解放を唱えていたとしたら、こんなに素晴らしいことはありません(^.^)/
そして、魂が煩悩から自由になることは、非常に重要なことなのだ、と思わざるをえません。
今日も最後まで読んでくださいまして、ありがとうございましたm(__)m
皆様に天使とマスターと共に祝福を贈ります☆

みなさんこんばんは(^^)
明日は節分ですね。豆まきで邪を払うもいいですし、今年の恵方である“南南東”の方角にある神社仏閣をお参りする「恵方参り」も良いですね(^_-)-☆

ところで、今日も『パイドン』(プラトン著 岩田靖夫訳 岩波文庫)を参考にしながら古代ギリシャの叡智をお伝えしたいと思います☆
ソクラテスは言います。肉体的なものにとらわれた魂は、目に見えないものやハデス(冥界)を恐れ、彼らは生前自分たちが実践してきたような性格の中へ入り込む、と。
例えば大食や好色、酒びたりの生活にひたり、これらを避けるための努力をしなかった人や、不正、独裁政治、掠奪(りゃくだつ)を好んで選んだ人たちは、彼らにふさわしいところに入っていく、ということですね。
一方で、幸福な人たち、最善の場所へ行く人たちは、「市民の公共の徳を実践してきた人たち」と言っています。
それは、思慮とか正義とかよばれている徳です。
これらの人たちは公共的で温和な中に再び生まれるということですね。
しかし神々の種族の仲間に入るのは、また違った人たちだと言います。
それは、哲学をした人、まったく清らかになって立ち去る人、学を愛する人であると。
本当の哲学者はすべての肉体的な欲望を避け、忍耐し、自分自身を欲望に委ねることをしないということですね。
お釈迦様やイエス様などの偉大なマスター達は、肉体的な欲望をしりぞけて、忍耐強くご自分の愛と叡智を分かち合っていかれました。
すばらしい哲学者ですね☆
それでは次回は、魂が受け取る恩恵と、魂が蒙る(こうむる)究極の悪とについてお伝えしたいと思います。
今日も読んでくださいまして、ありがとうございました(^<^)
明日は節分ですね。豆まきで邪を払うもいいですし、今年の恵方である“南南東”の方角にある神社仏閣をお参りする「恵方参り」も良いですね(^_-)-☆

ところで、今日も『パイドン』(プラトン著 岩田靖夫訳 岩波文庫)を参考にしながら古代ギリシャの叡智をお伝えしたいと思います☆
ソクラテスは言います。肉体的なものにとらわれた魂は、目に見えないものやハデス(冥界)を恐れ、彼らは生前自分たちが実践してきたような性格の中へ入り込む、と。
例えば大食や好色、酒びたりの生活にひたり、これらを避けるための努力をしなかった人や、不正、独裁政治、掠奪(りゃくだつ)を好んで選んだ人たちは、彼らにふさわしいところに入っていく、ということですね。
一方で、幸福な人たち、最善の場所へ行く人たちは、「市民の公共の徳を実践してきた人たち」と言っています。
それは、思慮とか正義とかよばれている徳です。
これらの人たちは公共的で温和な中に再び生まれるということですね。
しかし神々の種族の仲間に入るのは、また違った人たちだと言います。
それは、哲学をした人、まったく清らかになって立ち去る人、学を愛する人であると。
本当の哲学者はすべての肉体的な欲望を避け、忍耐し、自分自身を欲望に委ねることをしないということですね。
お釈迦様やイエス様などの偉大なマスター達は、肉体的な欲望をしりぞけて、忍耐強くご自分の愛と叡智を分かち合っていかれました。
すばらしい哲学者ですね☆
それでは次回は、魂が受け取る恩恵と、魂が蒙る(こうむる)究極の悪とについてお伝えしたいと思います。
今日も読んでくださいまして、ありがとうございました(^<^)
みなさんこんばんは
今回は魂のあり方についてのソクラテスの議論を、ご紹介していきたいと思います。
【 『パイドン』(プラトン著 岩田靖夫訳 岩波文庫)参考 】
ソクラテスは言います。もしも、魂が肉体を避け、自分自身へと集中していたならば、魂は肉体的な要素を少しも持つことはない、と。
そして肉体を避け自分自身へと集中することこそが、正しく哲学することであり、それは真実に平然と死ぬことを練習することに他ならない、と言います。(同書P79)
これに反して魂が汚れたまま浄められずに肉体から解放されることがあり、そういう魂は、肉体的な姿をしたもの、人が触ったり、見たり、飲んだり、食べたり、性の快楽のために用いたりするもの、こういったものを真実と思ってしまう、と言います。
これは絶えず肉体と共にあるために肉体に習熟してしまったためである、とも。
そしてこういう魂は肉眼には見えないが、知性によってとらえられ、また哲学によって把握されるようなものを憎み、恐れ、避けるように習慣づけられるとも言っています。
そしてソクラテスは、この肉体的なものは“重荷”である、と言います。
このような魂は、肉体的なものの欲望によって、再び肉体の中に巻き込まれるまで、さまよい続け、当然のごとく彼らは、生前自分たちが実践してきたような性格の中へ、入り込むのである、ということを弟子に伝えます。(P80~82)

哲学は自分自身へと集中する練習であり、そうすることはつまり、肉体にとらわれることなく、平然と死ぬことを練習しているようなものであるということになりますね。
肉体にとらわれていると、平然と死ぬことも難しいでしょう。どうしても肉体を去ることが怖くなってしまいますからね。
ここで誤解して頂きたくないのですが、ソクラテスは自殺に関しては勧めていませんし、肯定もしていません。
ソクラテスは言っています。われわれ人間はある牢獄の中にいて、そこから自分自身を解放して逃げ出してはならないのだ、と。
神々は、われわれ人間を配慮するものであり、人間は神々の所有物の1つである。
そのため、何らかの必然を神が送るまでは、自分自身を殺してはいけない、ということなんですね。(P24)
それでは、どのような魂があの世で歓迎されるのでしょうか?
次回をどうぞお楽しみに(^<^)

今回は魂のあり方についてのソクラテスの議論を、ご紹介していきたいと思います。
【 『パイドン』(プラトン著 岩田靖夫訳 岩波文庫)参考 】
ソクラテスは言います。もしも、魂が肉体を避け、自分自身へと集中していたならば、魂は肉体的な要素を少しも持つことはない、と。
そして肉体を避け自分自身へと集中することこそが、正しく哲学することであり、それは真実に平然と死ぬことを練習することに他ならない、と言います。(同書P79)
これに反して魂が汚れたまま浄められずに肉体から解放されることがあり、そういう魂は、肉体的な姿をしたもの、人が触ったり、見たり、飲んだり、食べたり、性の快楽のために用いたりするもの、こういったものを真実と思ってしまう、と言います。
これは絶えず肉体と共にあるために肉体に習熟してしまったためである、とも。
そしてこういう魂は肉眼には見えないが、知性によってとらえられ、また哲学によって把握されるようなものを憎み、恐れ、避けるように習慣づけられるとも言っています。
そしてソクラテスは、この肉体的なものは“重荷”である、と言います。
このような魂は、肉体的なものの欲望によって、再び肉体の中に巻き込まれるまで、さまよい続け、当然のごとく彼らは、生前自分たちが実践してきたような性格の中へ、入り込むのである、ということを弟子に伝えます。(P80~82)

哲学は自分自身へと集中する練習であり、そうすることはつまり、肉体にとらわれることなく、平然と死ぬことを練習しているようなものであるということになりますね。
肉体にとらわれていると、平然と死ぬことも難しいでしょう。どうしても肉体を去ることが怖くなってしまいますからね。
ここで誤解して頂きたくないのですが、ソクラテスは自殺に関しては勧めていませんし、肯定もしていません。
ソクラテスは言っています。われわれ人間はある牢獄の中にいて、そこから自分自身を解放して逃げ出してはならないのだ、と。
神々は、われわれ人間を配慮するものであり、人間は神々の所有物の1つである。
そのため、何らかの必然を神が送るまでは、自分自身を殺してはいけない、ということなんですね。(P24)
それでは、どのような魂があの世で歓迎されるのでしょうか?
次回をどうぞお楽しみに(^<^)
熊本もどんどん寒くなってきてますね。恐るべし大寒波
さて、今日も『パイドン』(プラトン著 岩田靖夫訳 岩波文庫)を通してソクラテス、そして著者のプラトンの叡智を探究していきたいと思います。
死後にも生まれる前と同様に魂は存続するという証明が展開をしていく中で、知恵のあり方について迫っていきます。

まずソクラテスは“目に見えるもの“と”目に見えないもの“という2種類の存在のあり方を立てます。
そして、“目に見えないもの”はいつも同じあり方を保って、“目に見えるもの”は決して同じあり方を保たないと決めます。
そして私たち自身の一部分は肉体であり、他の部分は魂ですが、肉体は2種類のあり方のどちらにより似ているかを弟子のケベスに尋ねます。
肉体は“目に見えるもの“により近いとケベスは答えます。
では、魂はどうかと聞かれると、“目に見えないもの”と答えます。
ところで、魂は何かを考える時に、見たり聞いたり、何か他の感覚を通して、肉体の助けを借りて行うわけですが、その時、魂は肉体によって一時も同じあり方を保たない方へと引きずり込まれ、魂自身がさまよい、混乱し、酔ったようになってめまいを覚えるものだとソクラテスは言います。
しかし、「魂が自分自身だけで考える時には、魂は純粋で、永遠で、不死で、同じようにあるものの方へと赴く。そして魂はそのようなものと親族なのだから、魂が純粋に自分自身だけになる場合は、さまようことを止め、永遠的なものと関わりながら、いつも同じあり方を保つ。なぜなら、魂はそういうものに触れるからである。そして、魂のこの状態こそが『知恵(フロネーシス)』と呼ばれるのではないか」(同P76)と、知恵と呼べる魂の状態について述べています。
知恵とは魂が肉体に捕われていない状態であり、のびのびと本来の魂らしくある状態ということでしょう。
肉体から魂を自由にすることが求められます。それについてソクラテスはさらに説明してくれます。
どうぞ続きをお楽しみに(^_-)

さて、今日も『パイドン』(プラトン著 岩田靖夫訳 岩波文庫)を通してソクラテス、そして著者のプラトンの叡智を探究していきたいと思います。
死後にも生まれる前と同様に魂は存続するという証明が展開をしていく中で、知恵のあり方について迫っていきます。

まずソクラテスは“目に見えるもの“と”目に見えないもの“という2種類の存在のあり方を立てます。
そして、“目に見えないもの”はいつも同じあり方を保って、“目に見えるもの”は決して同じあり方を保たないと決めます。
そして私たち自身の一部分は肉体であり、他の部分は魂ですが、肉体は2種類のあり方のどちらにより似ているかを弟子のケベスに尋ねます。
肉体は“目に見えるもの“により近いとケベスは答えます。
では、魂はどうかと聞かれると、“目に見えないもの”と答えます。
ところで、魂は何かを考える時に、見たり聞いたり、何か他の感覚を通して、肉体の助けを借りて行うわけですが、その時、魂は肉体によって一時も同じあり方を保たない方へと引きずり込まれ、魂自身がさまよい、混乱し、酔ったようになってめまいを覚えるものだとソクラテスは言います。
しかし、「魂が自分自身だけで考える時には、魂は純粋で、永遠で、不死で、同じようにあるものの方へと赴く。そして魂はそのようなものと親族なのだから、魂が純粋に自分自身だけになる場合は、さまようことを止め、永遠的なものと関わりながら、いつも同じあり方を保つ。なぜなら、魂はそういうものに触れるからである。そして、魂のこの状態こそが『知恵(フロネーシス)』と呼ばれるのではないか」(同P76)と、知恵と呼べる魂の状態について述べています。
知恵とは魂が肉体に捕われていない状態であり、のびのびと本来の魂らしくある状態ということでしょう。
肉体から魂を自由にすることが求められます。それについてソクラテスはさらに説明してくれます。
どうぞ続きをお楽しみに(^_-)
こんばんは(*^_^*)
1月も半月が経ちました。早いものですね!
さて、前回に引き続き古代ギリシャの哲学者ソクラテスによる“魂の不滅”についての考え方を、紹介させていただきたいと思います。
ソクラテスは魂の不滅について「想起(そうき)説」からも説明しています。
想起とは、思い出すという意味ですが、私たちは生まれる前に既に知識を得ており、地上に生まれる時にはそれを失ってしまいますが、そこから知識の対象について五感を使いながら、生まれる以前に知っていた“その知識“を再び把握するのだということですね。
そして、私たちが『学ぶこと』と呼んでいるものは、もともと自分のものであった知識をを再び把握することであり、それが「想起すること」であると言います。
日々の生活の中で、見るもの、聞くもの、触れるものなどをきっかけに私たちはもともと持っていた真実の知識(イデア)を思い出すのだということですね。
では「イデア」とはどのようなものでしょうか?
『まさにそのもの』、『原型』といえるものということですが、私たちに浮かんでくるイメージや感覚といってもいいかもしれません。
たとえば、地面から生えているものをみて「これは木だ」と思う時というのは、既に自分の中に“木”の原型のイメージがあって、それと似ているので「これは木だ」と思うわけですね。
また『美』や『善』、『徳』といった感覚も生まれる前から既に私たちは持っていて、様々な体験をする中で、この考えや行いは『善そのもの』であると思ったり、『善』ではないと思ったりしますね。
また何かを見ては『美そのもの』と感じたり、『美』ではないと思ったり、ちょっと欠けていると思ったりします。
私たちが感じたり考えたりする時の根本的な基準となる何か(イデア)を、生まれてくる前に既に持っているということをソクラテスはこのように言っています。
『魂は人間の形の中に入るまえにも、肉体から離れて存在していたのであり、知力をもっていたのだ』【『パイドン』(プラトン著 岩田靖夫訳 岩波文庫)P66】
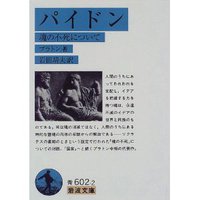
私たちは家庭や学校で「木」や「石」とはどういうものかを教えられたり、見たり触れたりして覚えていきます。
また美しい音楽や絵画なども学ぶことができます。
さらにしていいこと、悪いことといった道徳も学んでいきます。
ですが特に教えられずとも私たちの魂は既に知っていると感じることがあります。
例えば美しい自然を見て感動したり、鳥のさえずりをきれいだと感じたり、聖地や神社仏閣にお参りに行っては心がすがすがしくなったりしますね。
また自分が情熱を感じることや、これが正義だと思い行動することも、イデアに基づいている可能性があります。
教育で学ぶことや、日常生活の体験から学ぶことは、もともと魂が知っていることを再確認して、思い出すのを助けていること、というのが想起説の考え方ですね。
イデアをうまく思い出させるための教え方というものがとても大切になってきます。
たとえば『正義』というイデアをどのようにとらえて教えるのか。
正義は平等・公平の意味を持たなければなりません。
自分や自分たちの思いを通すための大義(たいぎ)が必ずしも『正義』と言えるとは限りません。
その『正義』の意味が公平と言う意味をもっているかどうか、価値を平等にみているのかどうか、そういうことが重要になってくると思います。
自分に対して、そして他人に対して正義をどのように教えるかは、真実の知識への橋渡しとなるか、それとも真実の知識とは遠く離れてしまうことになるのかの分かれ道となり得ます。
イデアに近づくのか、遠ざかっていくのか、これはとても重要な問題です。
なぜなら、イデアを探究して、近づいていくことが哲学の目的だからです。
“魂の不滅”についてのソクラテスと弟子たちの思索はまだ続きます(^<^)
今日も最後まで読んでくださいまして、ありがとうございました☆
1月も半月が経ちました。早いものですね!
さて、前回に引き続き古代ギリシャの哲学者ソクラテスによる“魂の不滅”についての考え方を、紹介させていただきたいと思います。
ソクラテスは魂の不滅について「想起(そうき)説」からも説明しています。
想起とは、思い出すという意味ですが、私たちは生まれる前に既に知識を得ており、地上に生まれる時にはそれを失ってしまいますが、そこから知識の対象について五感を使いながら、生まれる以前に知っていた“その知識“を再び把握するのだということですね。
そして、私たちが『学ぶこと』と呼んでいるものは、もともと自分のものであった知識をを再び把握することであり、それが「想起すること」であると言います。
日々の生活の中で、見るもの、聞くもの、触れるものなどをきっかけに私たちはもともと持っていた真実の知識(イデア)を思い出すのだということですね。
では「イデア」とはどのようなものでしょうか?
『まさにそのもの』、『原型』といえるものということですが、私たちに浮かんでくるイメージや感覚といってもいいかもしれません。
たとえば、地面から生えているものをみて「これは木だ」と思う時というのは、既に自分の中に“木”の原型のイメージがあって、それと似ているので「これは木だ」と思うわけですね。
また『美』や『善』、『徳』といった感覚も生まれる前から既に私たちは持っていて、様々な体験をする中で、この考えや行いは『善そのもの』であると思ったり、『善』ではないと思ったりしますね。
また何かを見ては『美そのもの』と感じたり、『美』ではないと思ったり、ちょっと欠けていると思ったりします。
私たちが感じたり考えたりする時の根本的な基準となる何か(イデア)を、生まれてくる前に既に持っているということをソクラテスはこのように言っています。
『魂は人間の形の中に入るまえにも、肉体から離れて存在していたのであり、知力をもっていたのだ』【『パイドン』(プラトン著 岩田靖夫訳 岩波文庫)P66】
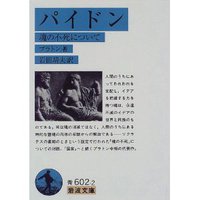
私たちは家庭や学校で「木」や「石」とはどういうものかを教えられたり、見たり触れたりして覚えていきます。
また美しい音楽や絵画なども学ぶことができます。
さらにしていいこと、悪いことといった道徳も学んでいきます。
ですが特に教えられずとも私たちの魂は既に知っていると感じることがあります。
例えば美しい自然を見て感動したり、鳥のさえずりをきれいだと感じたり、聖地や神社仏閣にお参りに行っては心がすがすがしくなったりしますね。
また自分が情熱を感じることや、これが正義だと思い行動することも、イデアに基づいている可能性があります。
教育で学ぶことや、日常生活の体験から学ぶことは、もともと魂が知っていることを再確認して、思い出すのを助けていること、というのが想起説の考え方ですね。
イデアをうまく思い出させるための教え方というものがとても大切になってきます。
たとえば『正義』というイデアをどのようにとらえて教えるのか。
正義は平等・公平の意味を持たなければなりません。
自分や自分たちの思いを通すための大義(たいぎ)が必ずしも『正義』と言えるとは限りません。
その『正義』の意味が公平と言う意味をもっているかどうか、価値を平等にみているのかどうか、そういうことが重要になってくると思います。
自分に対して、そして他人に対して正義をどのように教えるかは、真実の知識への橋渡しとなるか、それとも真実の知識とは遠く離れてしまうことになるのかの分かれ道となり得ます。
イデアに近づくのか、遠ざかっていくのか、これはとても重要な問題です。
なぜなら、イデアを探究して、近づいていくことが哲学の目的だからです。
“魂の不滅”についてのソクラテスと弟子たちの思索はまだ続きます(^<^)
今日も最後まで読んでくださいまして、ありがとうございました☆
『 魂は不滅 !? 』
おはようございます(^<^)
寒い中いかがお過ごしでしょうか?
さて、果たして魂は不滅なのかどうか、というとても大きな問題に対して答えてくれた先人がいます。
その偉大なマスターとは古代ギリシャの哲学者「ソクラテス」です(^.^)
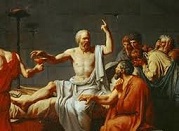
ソクラテスは紀元前469年頃~399年にギリシャで活躍としたと言われています。
宇宙の叡智を人々に広く分かち合っていましたが、「国家が信じる神々とは異なる神々を信じ、若者を堕落させた」という理由で裁判にかけられて、ついには死刑の宣告を受けました。
キリストとの共通点を感じますが、偉大なマスターは多くの困難を乗り越えていくものですね。
毒をあおって亡くなる直前に弟子たち(シミアスとケベス)と議論した内容が“魂の不滅”についてでした。
その内容は『パイドン』(プラトン著 岩田靖夫訳 岩波文庫)に書かれてます。
ソクラテスは魂の不滅を証明するための根拠を探究していきます。
その証明の中の1つについてご紹介しましょう。
ソクラテスはケベスに対して語りかけます。
(『パイドン』P48~引用)
ソクラテス(以下ソ)「たとえば、美が醜に反対であり、正が不正に反対であり、その他無数のものがそのような関係にあるのだが――そういうものにおいては、その一方は反対である他方からしか生じえないのだ、ということを」
そして彼はこのことを考察するためにいくつか例を挙げていきます。
たとえば、何かがより大きくなる時には必ず、その前により小さな状態にあって、そこからより大きくなるということや、その反対にそれがより小さくなるならば、以前のより大きな状態から後により小さくなるということを。
さらになにかがより悪くなるならば、それはより良い状態からであり、より正しくなるならば、より不正な状態からということを。
ソクラテスが言います。「すべての者は、反対のものが反対のものからという仕方で、生成するのだ、と」(同P49)
ちょっと頭がクラクラしてくるかもしれませんが(笑)、もう少しのお付き合いを♪
そこでケベスに問いかけます。
(P50)ソ「生きていることに対してなにか反対のものがあるかね。」
ケベス(以下ケ)「もちろん、ありますとも」
ソ「何だ」
ケ「死んでいることです」
(P51)ソ「君は死んでいることが生きていることに対して反対である、と言うのではないか」
ケ「そう言います」
ソ「それらはお互いから生ずるのだね」
ケ「はい」
ソ「では、生きているものから生ずるものは何か」
ケ「死んでいるものです」
ソ「死んでいるものからは何が生ずるのか」
ケ「生きているものが、と同意せざるをえません」
ソ「それなら、ケベス、死んでいるものたちから、生きているものたちや生きている人間たちが生まれるのだね」
ケ「そう思われます」
ソ「そうであれば、われわれの魂はハデス(冥界)に存在していることになる」
ケ「そのようです」
その後ソクラテスはとても興味深いことを話します。
それは、もし生を受けたものがすべて死んでゆき、死者はその状態に留まって再び生き返らないとするならば、最後には万物が死んで生きているものは何もなくなってしまうという話です。
ソクラテスが言います。(P54)「生き返るということも、生者が死者から生まれるということも、死者たちの魂が存在するということも、本当に有ることなのだ」
魂の不滅についての証明はほかにもありますので、続きは次回に☆
おはようございます(^<^)
寒い中いかがお過ごしでしょうか?
さて、果たして魂は不滅なのかどうか、というとても大きな問題に対して答えてくれた先人がいます。
その偉大なマスターとは古代ギリシャの哲学者「ソクラテス」です(^.^)
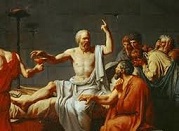
ソクラテスは紀元前469年頃~399年にギリシャで活躍としたと言われています。
宇宙の叡智を人々に広く分かち合っていましたが、「国家が信じる神々とは異なる神々を信じ、若者を堕落させた」という理由で裁判にかけられて、ついには死刑の宣告を受けました。
キリストとの共通点を感じますが、偉大なマスターは多くの困難を乗り越えていくものですね。
毒をあおって亡くなる直前に弟子たち(シミアスとケベス)と議論した内容が“魂の不滅”についてでした。
その内容は『パイドン』(プラトン著 岩田靖夫訳 岩波文庫)に書かれてます。
ソクラテスは魂の不滅を証明するための根拠を探究していきます。
その証明の中の1つについてご紹介しましょう。
ソクラテスはケベスに対して語りかけます。
(『パイドン』P48~引用)
ソクラテス(以下ソ)「たとえば、美が醜に反対であり、正が不正に反対であり、その他無数のものがそのような関係にあるのだが――そういうものにおいては、その一方は反対である他方からしか生じえないのだ、ということを」
そして彼はこのことを考察するためにいくつか例を挙げていきます。
たとえば、何かがより大きくなる時には必ず、その前により小さな状態にあって、そこからより大きくなるということや、その反対にそれがより小さくなるならば、以前のより大きな状態から後により小さくなるということを。
さらになにかがより悪くなるならば、それはより良い状態からであり、より正しくなるならば、より不正な状態からということを。
ソクラテスが言います。「すべての者は、反対のものが反対のものからという仕方で、生成するのだ、と」(同P49)
ちょっと頭がクラクラしてくるかもしれませんが(笑)、もう少しのお付き合いを♪
そこでケベスに問いかけます。
(P50)ソ「生きていることに対してなにか反対のものがあるかね。」
ケベス(以下ケ)「もちろん、ありますとも」
ソ「何だ」
ケ「死んでいることです」
(P51)ソ「君は死んでいることが生きていることに対して反対である、と言うのではないか」
ケ「そう言います」
ソ「それらはお互いから生ずるのだね」
ケ「はい」
ソ「では、生きているものから生ずるものは何か」
ケ「死んでいるものです」
ソ「死んでいるものからは何が生ずるのか」
ケ「生きているものが、と同意せざるをえません」
ソ「それなら、ケベス、死んでいるものたちから、生きているものたちや生きている人間たちが生まれるのだね」
ケ「そう思われます」
ソ「そうであれば、われわれの魂はハデス(冥界)に存在していることになる」
ケ「そのようです」
その後ソクラテスはとても興味深いことを話します。
それは、もし生を受けたものがすべて死んでゆき、死者はその状態に留まって再び生き返らないとするならば、最後には万物が死んで生きているものは何もなくなってしまうという話です。
ソクラテスが言います。(P54)「生き返るということも、生者が死者から生まれるということも、死者たちの魂が存在するということも、本当に有ることなのだ」
魂の不滅についての証明はほかにもありますので、続きは次回に☆
『パイドン』(プラトン著 岩田靖夫訳 岩波文庫)より霊魂の不滅の証明についてのギリシャの哲学者ソクラテスの考えをご紹介したいと思います。
尚、この作品はソクラテスが服毒による刑死を控え、獄中で弟子たち(シミアスとケベス)と哲学的対話をするものです。
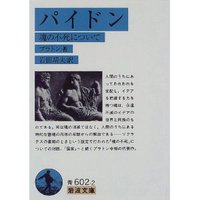
魂の存在についての議論のあとに「想起説」が続きます。
【P55~】
ケベス あなたがよく話しておられたあの理論―それは、われわれの学習は想起にほかならないというあの理論ですが―それにしたがってもまた、もしそれが真実であれば、われわれはなにか以前の時に、現在想起していることを学んでしまっている、ということにならざるを得ません。
だが、このことは、もしもわれわれの魂がこの人間の形の中に入る前に、どこか存在していたのでなかったならば、不可能です。だから、この点からも、魂がなにか不死なるものである、思われるのです
シミアスが口を挟みました。「その証明はどんなだっけ。思い出させてくれないか」
ケベス 一つのもっとも美しい論証は…人々は質問されると、もし上手に質問が行われれば、どんなことについてでも、それが真実にはどう有るかということを、自力で言うことができる、ということだ。
だが、もしも、人々のうちに予め知識や正しい説明が内在していたのでなかったならば、このことをするのは不可能だったろう。さらに、また、幾何学の図形やなにか他のその種のものを例に用いれば、そこで、この通りであるということが、この上なく明らかに証明されるだろう
ソクラテスが『メノン』(プラトン著 藤沢令夫訳 岩波文庫)の中でメノン(貴族の子息)の召使の少年に対して図形についての質問を繰り返していき、少年から答えを導いていくという興味深い場面が登場します。

ソクラテスは召使の少年に正方形ABCDの2倍の面積になる正方形の導き方を尋ねていきます。 そこの場面を引用してご紹介します。
【メノンP61~】
ソクラテス 〔召使に向かって〕では、君、答えてくれたまえ。――ここに四〔平方〕プゥスの大きさの図形〔正方形ABCD〕がある。わかるね?
召使 ええ
ソクラテスここに、もうひとつ別の等しい図形〔BKPC〕を、これにつけ加えることができるね?
召使 はい
ソクラテス さらに、このどちらとも等しい第三番目のもの〔CPLQ〕を、ここに付け加えることができるね?
召使 はい
ソクラテス この角のあいているところを、これ〔DCQM〕をつけ加えてうずめることができるね?
召使 たしかに
ソクラテス そうすると、ここに四つの等しい図形ができることになるね?
召使 はい
ソクラテス で、どうだろう――この全体〔AKLM〕は、これ〔ABCD〕の何倍になるだろうか?
召使 四倍です
ソクラテス しかるにわれわれには、二倍の大きさのものができなければならないのだった。おぼえていないかね?
召使 たしかにそうでした
ソクラテス では、こういうふうに角から角へ線〔BDその他〕をひいて行くと、これらの図形のひとつひとつを二分することになるのではないかね?
召使 はい
ソクラテス そうすると、これら四つの等しい線〔DB・BP・PQ・QD〕ができて、この図形〔DBPQ〕をとりかこむことになるね。
召使 ええ、そういうことになります
ソクラテス さあ考えてごらん――この図形〔DBPQ〕の大きさはいくらだろうか?
召使 わかりません
ソクラテス このひとつひとつの腺〔DB・BP・PQ・QD〕は、ここに四つの図形があるが、そのおのおのの半分ずつを内側に切りとっているのではないか。ね?
召使 はい
ソクラテス では、半分に切りとられたそれだけの大きさのものが、これ〔DBPQ〕の中にいくつあるかね?
召使 四つあります
ソクラテス これ〔ABCD〕の中にはいくつあるかね?
召使 二つあります
ソクラテス 四つは二つの何にあたるかね?
召使 二倍です
ソクラテス そうすると、これ〔DBPQ〕は何〔平方〕プゥスになるかね?
召使 八〔平方〕プゥスです
ソクラテス どのような腺からできているかね?
召使 これ〔DB〕です
ソクラテス 四〔平方〕プゥスの大きさの図形の、角から角へひいた線のことだね?
召使 はい
ソクラテス 学者たちはこの線のことを、対角線と呼んでいるのだよ。
だから対角線というのがこれの名前だとすると、メノンに仕える子よ、君の主張は、対角線を一辺として二倍の正方形はできるのだということになるだろう
召使 たしかにそのとおりです、ソクラテス
ソクラテス どう思う?メノン。この子が答えたことで、この子自身の思わく(思いなし)ではないようなものが、ひとつでもあっただろうか
メノン いいえ、自分でそう思ったことばかりでした
ソクラテス しかし、われわれがすこし前に言っていたように、もともとこの子は、こうしたことを知ってはいなかったのだ
メノン おっしゃるとおりです
ソクラテス ただしかし、この子の中には、この子がいま述べたようないろいろの思わくが内在していたということはたしかだ。そうではないだろうか?
メノン ええ
ソクラテス とすると、ものを知らない人の中には、何を知らないにせよ、彼が知らないその当の事柄に関する正しい思わくが内在しているということになるね?
メノン 明らかにそうです
ソクラテス そしてこの子にとって、これらいろいろの思わくは、いまでこそ、ちょうど夢のように、よびさまされたばかりの状態にあるわけだけれども、しかしもし誰かが、こうした同じ事柄を何度もいろいろのやり方でたずねるならば、最後には、この子はこうした事柄について、誰にも負けないくらい正確な知識をもつようになるだろうということは、うけあってもいいだろう
メノン そうでしょうね
ソクラテス それは、誰かがこの子に教えたからというわけではなく、ただ質問した結果として、この子は自分で自分の中から知識をふたたび取り出し、それによって知識をもつようになるのではないかね?
メノン そうです
ソクラテス しかるに、自分で自分の中に知識をふたたび把握し直すということは、想起するということにほかならないのではないだろうか?
メノン ええ
ソクラテス で、もしつねにもちつづけていたというほうの前提をとれば、この子はまた、つねに知識をもっている人であったということになるし、他方また、いつか以前に得たのだとしても、すくなくとも現在のこの生においてそれを得たことにはならないだろう。――それとも誰か、この子に幾何のやり方を教えこんだ者がいるのかね?
なぜって、この子はきっと、幾何学のどんな問題についても、同じようにこういったことをするだろうからね。さらには、ほかのあらゆる学問についても――。
さあ、誰かこの子に、何もかも教えてしまったものがいるのかね?君は当然知っているはずだ。とくに、この子が君の家で生まれ、君の家で育てられたというのならば
メノン いいえ、私はよく知っていますが、これまで誰もこの子に教えた者はいません
ソクラテス それなのにこの子は、さっきのようないろいろの思わくをちゃんともっているのだ。そうではないかね?
メノン それは、ソクラテス、否定できないようです
【中略】
ソクラテス そこで、もしこの子が人間であったときにも、人間として生まれていなかったときにも、同じように正しい思わくがこの子の中に内在していて、それが質問によってよびさまされたうえで知識となるというべきならば、この子の魂は、あらゆるときにわたって、つねに学んでしまっている状態にあるのではないだろうか?
なぜなら明らかに、この子はあらゆる時を通じて、人間であるか人間でないかの、どちらかなのだから
メノン 明らかにそういうことになります
ソクラテス そこで、もしわれわれにとって、もろもろの事物に関する真実がつねに魂の中にあるのだとするならば、魂とは不死のものだということになるのではないだろうか。
したがって、いまたまたま君が知識をもっていないような事柄があったとしても――ということはつまり、想い出していないということなのだが――心をはげましてそれを探究し、想起するようにつとめるべきではないだろうか?
メノン あなたのおっしゃることには、ソクラテス、なぜかはしりませんが、たしかになるほどと思わせるものがあるようです
☆★☆★☆
ソクラテスが召使の子供に対して、正方形ABCDの2倍の面積の正方形の求め方を導いていますね。
正方形の対角線は√2の長さになりますから、面積は√2×√2=2 ということで確かに2倍になりますね。
それをより分かりやすく四角形や三角形の図形の数を使って子どもを導いています。
この設問の答えは誰が教えずともすでに彼の中にあるもので、それは魂が持っている叡智であり、魂は絶えることなくあらゆる時代にあらゆる経験をしてその叡智を蓄えているということをソクラテスは言っています。
魂の不滅性です。
魂が不滅で実はなんでも知っているんだという前提に立つと、例えば教育においても子供や生徒への接し方が変わってくるのではないでしょうか。
目の前の子どもや生徒には教えないとわからない、というスタンスで臨むのと、相手のもともと持っている叡智が想起されるようにサポートをしていく、というスタンスで臨むのとでは、教え方も学び方も違ってくるでしょう。
想起させるための導き方が重要になってきますね。
ソクラテスは召使の子供に対して、すでにこの子には叡智が備わっているという前提で導いていますね。参考になる方法ではないでしょうか。
占星術のレッスンやセミナーにおいて申し上げますと、私がお教えすることは、受講される方がご自分の叡智を思い出すための一つのきっかけであると思っています。
ご自分も同じ考え、叡智を持っていることを思い出される方もいらっしゃるでしょう。
またご自分はその考えとは違う叡智をもっているということを思い出される方もいらっしゃるでしょう。
お一人お一人の魂の叡智を認めて尊重することは、大切なエンパワーメントだと思います。
これからさらに魂の不滅性についての探究が続きますよ!
どうぞお楽しみに(^_-)-☆
尚、この作品はソクラテスが服毒による刑死を控え、獄中で弟子たち(シミアスとケベス)と哲学的対話をするものです。
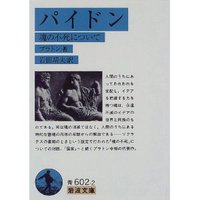
魂の存在についての議論のあとに「想起説」が続きます。
【P55~】
ケベス あなたがよく話しておられたあの理論―それは、われわれの学習は想起にほかならないというあの理論ですが―それにしたがってもまた、もしそれが真実であれば、われわれはなにか以前の時に、現在想起していることを学んでしまっている、ということにならざるを得ません。
だが、このことは、もしもわれわれの魂がこの人間の形の中に入る前に、どこか存在していたのでなかったならば、不可能です。だから、この点からも、魂がなにか不死なるものである、思われるのです
シミアスが口を挟みました。「その証明はどんなだっけ。思い出させてくれないか」
ケベス 一つのもっとも美しい論証は…人々は質問されると、もし上手に質問が行われれば、どんなことについてでも、それが真実にはどう有るかということを、自力で言うことができる、ということだ。
だが、もしも、人々のうちに予め知識や正しい説明が内在していたのでなかったならば、このことをするのは不可能だったろう。さらに、また、幾何学の図形やなにか他のその種のものを例に用いれば、そこで、この通りであるということが、この上なく明らかに証明されるだろう
ソクラテスが『メノン』(プラトン著 藤沢令夫訳 岩波文庫)の中でメノン(貴族の子息)の召使の少年に対して図形についての質問を繰り返していき、少年から答えを導いていくという興味深い場面が登場します。

ソクラテスは召使の少年に正方形ABCDの2倍の面積になる正方形の導き方を尋ねていきます。 そこの場面を引用してご紹介します。
【メノンP61~】
ソクラテス 〔召使に向かって〕では、君、答えてくれたまえ。――ここに四〔平方〕プゥスの大きさの図形〔正方形ABCD〕がある。わかるね?
召使 ええ
ソクラテスここに、もうひとつ別の等しい図形〔BKPC〕を、これにつけ加えることができるね?
召使 はい
ソクラテス さらに、このどちらとも等しい第三番目のもの〔CPLQ〕を、ここに付け加えることができるね?
召使 はい
ソクラテス この角のあいているところを、これ〔DCQM〕をつけ加えてうずめることができるね?
召使 たしかに
ソクラテス そうすると、ここに四つの等しい図形ができることになるね?
召使 はい
ソクラテス で、どうだろう――この全体〔AKLM〕は、これ〔ABCD〕の何倍になるだろうか?
召使 四倍です
ソクラテス しかるにわれわれには、二倍の大きさのものができなければならないのだった。おぼえていないかね?
召使 たしかにそうでした
ソクラテス では、こういうふうに角から角へ線〔BDその他〕をひいて行くと、これらの図形のひとつひとつを二分することになるのではないかね?
召使 はい
ソクラテス そうすると、これら四つの等しい線〔DB・BP・PQ・QD〕ができて、この図形〔DBPQ〕をとりかこむことになるね。
召使 ええ、そういうことになります
ソクラテス さあ考えてごらん――この図形〔DBPQ〕の大きさはいくらだろうか?
召使 わかりません
ソクラテス このひとつひとつの腺〔DB・BP・PQ・QD〕は、ここに四つの図形があるが、そのおのおのの半分ずつを内側に切りとっているのではないか。ね?
召使 はい
ソクラテス では、半分に切りとられたそれだけの大きさのものが、これ〔DBPQ〕の中にいくつあるかね?
召使 四つあります
ソクラテス これ〔ABCD〕の中にはいくつあるかね?
召使 二つあります
ソクラテス 四つは二つの何にあたるかね?
召使 二倍です
ソクラテス そうすると、これ〔DBPQ〕は何〔平方〕プゥスになるかね?
召使 八〔平方〕プゥスです
ソクラテス どのような腺からできているかね?
召使 これ〔DB〕です
ソクラテス 四〔平方〕プゥスの大きさの図形の、角から角へひいた線のことだね?
召使 はい
ソクラテス 学者たちはこの線のことを、対角線と呼んでいるのだよ。
だから対角線というのがこれの名前だとすると、メノンに仕える子よ、君の主張は、対角線を一辺として二倍の正方形はできるのだということになるだろう
召使 たしかにそのとおりです、ソクラテス
ソクラテス どう思う?メノン。この子が答えたことで、この子自身の思わく(思いなし)ではないようなものが、ひとつでもあっただろうか
メノン いいえ、自分でそう思ったことばかりでした
ソクラテス しかし、われわれがすこし前に言っていたように、もともとこの子は、こうしたことを知ってはいなかったのだ
メノン おっしゃるとおりです
ソクラテス ただしかし、この子の中には、この子がいま述べたようないろいろの思わくが内在していたということはたしかだ。そうではないだろうか?
メノン ええ
ソクラテス とすると、ものを知らない人の中には、何を知らないにせよ、彼が知らないその当の事柄に関する正しい思わくが内在しているということになるね?
メノン 明らかにそうです
ソクラテス そしてこの子にとって、これらいろいろの思わくは、いまでこそ、ちょうど夢のように、よびさまされたばかりの状態にあるわけだけれども、しかしもし誰かが、こうした同じ事柄を何度もいろいろのやり方でたずねるならば、最後には、この子はこうした事柄について、誰にも負けないくらい正確な知識をもつようになるだろうということは、うけあってもいいだろう
メノン そうでしょうね
ソクラテス それは、誰かがこの子に教えたからというわけではなく、ただ質問した結果として、この子は自分で自分の中から知識をふたたび取り出し、それによって知識をもつようになるのではないかね?
メノン そうです
ソクラテス しかるに、自分で自分の中に知識をふたたび把握し直すということは、想起するということにほかならないのではないだろうか?
メノン ええ
ソクラテス で、もしつねにもちつづけていたというほうの前提をとれば、この子はまた、つねに知識をもっている人であったということになるし、他方また、いつか以前に得たのだとしても、すくなくとも現在のこの生においてそれを得たことにはならないだろう。――それとも誰か、この子に幾何のやり方を教えこんだ者がいるのかね?
なぜって、この子はきっと、幾何学のどんな問題についても、同じようにこういったことをするだろうからね。さらには、ほかのあらゆる学問についても――。
さあ、誰かこの子に、何もかも教えてしまったものがいるのかね?君は当然知っているはずだ。とくに、この子が君の家で生まれ、君の家で育てられたというのならば
メノン いいえ、私はよく知っていますが、これまで誰もこの子に教えた者はいません
ソクラテス それなのにこの子は、さっきのようないろいろの思わくをちゃんともっているのだ。そうではないかね?
メノン それは、ソクラテス、否定できないようです
【中略】
ソクラテス そこで、もしこの子が人間であったときにも、人間として生まれていなかったときにも、同じように正しい思わくがこの子の中に内在していて、それが質問によってよびさまされたうえで知識となるというべきならば、この子の魂は、あらゆるときにわたって、つねに学んでしまっている状態にあるのではないだろうか?
なぜなら明らかに、この子はあらゆる時を通じて、人間であるか人間でないかの、どちらかなのだから
メノン 明らかにそういうことになります
ソクラテス そこで、もしわれわれにとって、もろもろの事物に関する真実がつねに魂の中にあるのだとするならば、魂とは不死のものだということになるのではないだろうか。
したがって、いまたまたま君が知識をもっていないような事柄があったとしても――ということはつまり、想い出していないということなのだが――心をはげましてそれを探究し、想起するようにつとめるべきではないだろうか?
メノン あなたのおっしゃることには、ソクラテス、なぜかはしりませんが、たしかになるほどと思わせるものがあるようです
☆★☆★☆
ソクラテスが召使の子供に対して、正方形ABCDの2倍の面積の正方形の求め方を導いていますね。
正方形の対角線は√2の長さになりますから、面積は√2×√2=2 ということで確かに2倍になりますね。
それをより分かりやすく四角形や三角形の図形の数を使って子どもを導いています。
この設問の答えは誰が教えずともすでに彼の中にあるもので、それは魂が持っている叡智であり、魂は絶えることなくあらゆる時代にあらゆる経験をしてその叡智を蓄えているということをソクラテスは言っています。
魂の不滅性です。
魂が不滅で実はなんでも知っているんだという前提に立つと、例えば教育においても子供や生徒への接し方が変わってくるのではないでしょうか。
目の前の子どもや生徒には教えないとわからない、というスタンスで臨むのと、相手のもともと持っている叡智が想起されるようにサポートをしていく、というスタンスで臨むのとでは、教え方も学び方も違ってくるでしょう。
想起させるための導き方が重要になってきますね。
ソクラテスは召使の子供に対して、すでにこの子には叡智が備わっているという前提で導いていますね。参考になる方法ではないでしょうか。
占星術のレッスンやセミナーにおいて申し上げますと、私がお教えすることは、受講される方がご自分の叡智を思い出すための一つのきっかけであると思っています。
ご自分も同じ考え、叡智を持っていることを思い出される方もいらっしゃるでしょう。
またご自分はその考えとは違う叡智をもっているということを思い出される方もいらっしゃるでしょう。
お一人お一人の魂の叡智を認めて尊重することは、大切なエンパワーメントだと思います。
これからさらに魂の不滅性についての探究が続きますよ!
どうぞお楽しみに(^_-)-☆




