こんばんは(*^_^*)
1月も半月が経ちました。早いものですね!
さて、前回に引き続き古代ギリシャの哲学者ソクラテスによる“魂の不滅”についての考え方を、紹介させていただきたいと思います。
ソクラテスは魂の不滅について「想起(そうき)説」からも説明しています。
想起とは、思い出すという意味ですが、私たちは生まれる前に既に知識を得ており、地上に生まれる時にはそれを失ってしまいますが、そこから知識の対象について五感を使いながら、生まれる以前に知っていた“その知識“を再び把握するのだということですね。
そして、私たちが『学ぶこと』と呼んでいるものは、もともと自分のものであった知識をを再び把握することであり、それが「想起すること」であると言います。
日々の生活の中で、見るもの、聞くもの、触れるものなどをきっかけに私たちはもともと持っていた真実の知識(イデア)を思い出すのだということですね。
では「イデア」とはどのようなものでしょうか?
『まさにそのもの』、『原型』といえるものということですが、私たちに浮かんでくるイメージや感覚といってもいいかもしれません。
たとえば、地面から生えているものをみて「これは木だ」と思う時というのは、既に自分の中に“木”の原型のイメージがあって、それと似ているので「これは木だ」と思うわけですね。
また『美』や『善』、『徳』といった感覚も生まれる前から既に私たちは持っていて、様々な体験をする中で、この考えや行いは『善そのもの』であると思ったり、『善』ではないと思ったりしますね。
また何かを見ては『美そのもの』と感じたり、『美』ではないと思ったり、ちょっと欠けていると思ったりします。
私たちが感じたり考えたりする時の根本的な基準となる何か(イデア)を、生まれてくる前に既に持っているということをソクラテスはこのように言っています。
『魂は人間の形の中に入るまえにも、肉体から離れて存在していたのであり、知力をもっていたのだ』【『パイドン』(プラトン著 岩田靖夫訳 岩波文庫)P66】
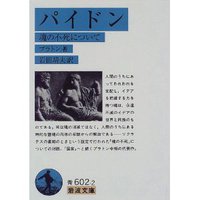
私たちは家庭や学校で「木」や「石」とはどういうものかを教えられたり、見たり触れたりして覚えていきます。
また美しい音楽や絵画なども学ぶことができます。
さらにしていいこと、悪いことといった道徳も学んでいきます。
ですが特に教えられずとも私たちの魂は既に知っていると感じることがあります。
例えば美しい自然を見て感動したり、鳥のさえずりをきれいだと感じたり、聖地や神社仏閣にお参りに行っては心がすがすがしくなったりしますね。
また自分が情熱を感じることや、これが正義だと思い行動することも、イデアに基づいている可能性があります。
教育で学ぶことや、日常生活の体験から学ぶことは、もともと魂が知っていることを再確認して、思い出すのを助けていること、というのが想起説の考え方ですね。
イデアをうまく思い出させるための教え方というものがとても大切になってきます。
たとえば『正義』というイデアをどのようにとらえて教えるのか。
正義は平等・公平の意味を持たなければなりません。
自分や自分たちの思いを通すための大義(たいぎ)が必ずしも『正義』と言えるとは限りません。
その『正義』の意味が公平と言う意味をもっているかどうか、価値を平等にみているのかどうか、そういうことが重要になってくると思います。
自分に対して、そして他人に対して正義をどのように教えるかは、真実の知識への橋渡しとなるか、それとも真実の知識とは遠く離れてしまうことになるのかの分かれ道となり得ます。
イデアに近づくのか、遠ざかっていくのか、これはとても重要な問題です。
なぜなら、イデアを探究して、近づいていくことが哲学の目的だからです。
“魂の不滅”についてのソクラテスと弟子たちの思索はまだ続きます(^<^)
今日も最後まで読んでくださいまして、ありがとうございました☆
1月も半月が経ちました。早いものですね!
さて、前回に引き続き古代ギリシャの哲学者ソクラテスによる“魂の不滅”についての考え方を、紹介させていただきたいと思います。
ソクラテスは魂の不滅について「想起(そうき)説」からも説明しています。
想起とは、思い出すという意味ですが、私たちは生まれる前に既に知識を得ており、地上に生まれる時にはそれを失ってしまいますが、そこから知識の対象について五感を使いながら、生まれる以前に知っていた“その知識“を再び把握するのだということですね。
そして、私たちが『学ぶこと』と呼んでいるものは、もともと自分のものであった知識をを再び把握することであり、それが「想起すること」であると言います。
日々の生活の中で、見るもの、聞くもの、触れるものなどをきっかけに私たちはもともと持っていた真実の知識(イデア)を思い出すのだということですね。
では「イデア」とはどのようなものでしょうか?
『まさにそのもの』、『原型』といえるものということですが、私たちに浮かんでくるイメージや感覚といってもいいかもしれません。
たとえば、地面から生えているものをみて「これは木だ」と思う時というのは、既に自分の中に“木”の原型のイメージがあって、それと似ているので「これは木だ」と思うわけですね。
また『美』や『善』、『徳』といった感覚も生まれる前から既に私たちは持っていて、様々な体験をする中で、この考えや行いは『善そのもの』であると思ったり、『善』ではないと思ったりしますね。
また何かを見ては『美そのもの』と感じたり、『美』ではないと思ったり、ちょっと欠けていると思ったりします。
私たちが感じたり考えたりする時の根本的な基準となる何か(イデア)を、生まれてくる前に既に持っているということをソクラテスはこのように言っています。
『魂は人間の形の中に入るまえにも、肉体から離れて存在していたのであり、知力をもっていたのだ』【『パイドン』(プラトン著 岩田靖夫訳 岩波文庫)P66】
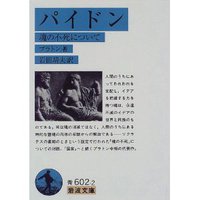
私たちは家庭や学校で「木」や「石」とはどういうものかを教えられたり、見たり触れたりして覚えていきます。
また美しい音楽や絵画なども学ぶことができます。
さらにしていいこと、悪いことといった道徳も学んでいきます。
ですが特に教えられずとも私たちの魂は既に知っていると感じることがあります。
例えば美しい自然を見て感動したり、鳥のさえずりをきれいだと感じたり、聖地や神社仏閣にお参りに行っては心がすがすがしくなったりしますね。
また自分が情熱を感じることや、これが正義だと思い行動することも、イデアに基づいている可能性があります。
教育で学ぶことや、日常生活の体験から学ぶことは、もともと魂が知っていることを再確認して、思い出すのを助けていること、というのが想起説の考え方ですね。
イデアをうまく思い出させるための教え方というものがとても大切になってきます。
たとえば『正義』というイデアをどのようにとらえて教えるのか。
正義は平等・公平の意味を持たなければなりません。
自分や自分たちの思いを通すための大義(たいぎ)が必ずしも『正義』と言えるとは限りません。
その『正義』の意味が公平と言う意味をもっているかどうか、価値を平等にみているのかどうか、そういうことが重要になってくると思います。
自分に対して、そして他人に対して正義をどのように教えるかは、真実の知識への橋渡しとなるか、それとも真実の知識とは遠く離れてしまうことになるのかの分かれ道となり得ます。
イデアに近づくのか、遠ざかっていくのか、これはとても重要な問題です。
なぜなら、イデアを探究して、近づいていくことが哲学の目的だからです。
“魂の不滅”についてのソクラテスと弟子たちの思索はまだ続きます(^<^)
今日も最後まで読んでくださいまして、ありがとうございました☆



